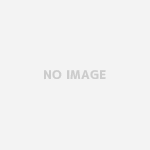「ネーミングセンスがない…」と思ったときに試してみたい3つの言動
最近、親族から集めた情報の中に同じケースが偶然まじっていたので、記事にしてみます。
子どもを育てていると「どうせ、自分はダメだもん。できないもん!」というようなセリフを聞く機会は多いのではないでしょうか。
定型の子だろうと非定型の子だろうと、苦手なことを学校の課題などでやらないといけないときには、特にこういう「もう嫌だ!」という気持ちと「頑張ったってできない!」という、成功する気配の片りんも感じられないことから早々に自分にギブアップする、ということはあると思います。
ただ発達障害の子を育てていると、この傾向が特に強い子がいたりします。その子達が見せる言動には
・あきらめやすい
・好きなことには兆戦できても、苦手なことはあえてしたくない
・一度やってみて失敗したり、思ったような結果にならなければ「次もきっとそうなる」という意識が支配して、前向きになれずネガティブになる
・嫌だ!無理だ!と一度思い始めると、その時にいくら親から励まされようと、誰かがやり方を優しく教えてくれようと、逆に「無理!絶対無理!」と言い張って抵抗するか、時には泣き叫んで我を忘れる
という点がくっきりと見えることがあります。きっと、色々、内面で悩んだり葛藤したりしているのだと思います。「過去の経験」から出した、自分なりの結論や方法論で、継続してそういう風に自分を守りながら日々の困りごとをに対抗していこうとしている「子どもながらの」自分のスキル内での戦いなんだろうな、と感じることもあります。
こうした発言をする親族の子達を同年齢の子達と比較してしまうと、幼稚園・小学生の時期は特に発達の凹み部分は同級生よりも1年や2年の遅れという差があることはざらなので、比べること自体が「今はふさわしくない」状態です。
でも当然、その発達凹み部分を意識していない大人側は「何でこの子は、こんなことも、こんなにできないんだろう」と自然と思うはずですし、それよりも先に
「手を抜いてる」
「努力が足りない」
「もう少し粘らないと、いい結果なんて出ない」
「ちょいちょいと最小限の時間と練習でさーっと完璧に成功レベルまでやれる人は少ない。なのに図々しくも『ほんのちょっと』の努力で『すぐに成功』することを願うなんて、甘すぎる」
という感想が、親や先生、大人側には湧いてきてしまうのではないかと思います。
この図々しく良い結果を求める発達障害の子は、はたして、どんな思考回路で物事にあたってるんだろう?という部分を解説したいので、具体的に親族の子の実例を下に書き記していきます。
小学校でリコーダーの音楽のテストを控えた子がいました。この子はテストの前に練習を「ほんの1回か2回」しただけで、絶対無理、自分は頑張ってもできないんだ!と泣き叫んで床に転がったりして騒ぎました。その親は、正直呆れて、すぐに無理と結論だすなんて、もともとやる気ないでしょう、と指摘したくもなりました。
毎回、こうした指摘をすると、発達障害の子はそうした大人の指摘は「よく記憶してしまう」ような部分があります。ですので、励ましたりしても、例え子のためと思って好意的に「本人の状態がどんなであるかを、客観的に情報として教えてみよう」と本人の状態を説明したりしたとしても、逆に子をネガティブな考え方に追いやってしまう時もあります。
子どもが精神的にダウンしたりめりこんでいきそうな時は避けた方がいいのですが、日々、何かと丁寧に説明したり親子で療育的な学びをしている中で、それでも時々、課題に対応しようとする時に「同じ理由での泣き叫び」をする場合は、課題10回に1回ぐらいの割合で「時間を数時間、もしくは1日たっぷりとって、一つのことをやりつくさせる」という「結果は下手でも失敗でもやりつくす」ことを経験させてもいいかと思います。
発達障害の子に「ずっと、365日、ストレスのない生活」をさせようと目指すのは人間が営む生活の中では不可能な話であり、いずれ大人になれば向き合わなくてはならない課題には責任や金銭などもからみ、あきらかにストレスに対応していかないといけなくなります。
ですので、その大人になった時に無難にやっていけるための予行練習は当然、子供時代には必要となります。「回数は少ないかもしれないけれど、とことん頑張ってみたり、思いっきり泣いたり苦しんだりしながらもやり通す」というようなことを、子どもならではの「失敗が許される学ぶ時期」をあえて利用して、経験させることは大事でもあります。
本人の精神状態やその時の状況などタイミングが大事ですが、二次障害でもなく、精神的にまあ健康な状態にあり、そこそこ安定しているという時には、私達は「ちょいと、とことんやり通す、という試みのための応援をしてみよう」と仕掛けることもあります。
リコーダーの子の話の続きに戻ります。親族はリコーダーのテストの練習を、週末の1日をつぶして、ああじゃない、こうじゃない、と色々と方法を変えながら、「無理!もう絶対できない!」とか「音がでなくなった!」とか、あーだこーだとごねる子に一歩も引かずに「暗記するぐらいまでやる」ということを試みたそうです。
どんな状態から、どこまで達成したかというと
・一人で練習を始めた時は、楽譜を見てもうろ覚えで、とちりまくって吹いていた
・まともな音ではなく、へろへろ、ピーっと音が割れる、など基本もなにもない、ただ空気をリコーダーに吹いて入れてるだけの状態。
・1回の演奏で何度もやり直すので「何の曲かすらわからない」状態で、本人も「何度もまちがって面倒、しんどい、大変、これを間違わずに吹くなんてありえない」と思い込んで、すでに2回目を吹く時には投げやり。
・親に何とかしてもらおうと「手助けして」っぽいことを言ってくるけど、実際に「何かアドバイス的なこと」をちらっとでも親が発言すると、とたんにキレたように反論するか、泣き叫ぶか、どうせでき
ない!とわめくかで、親のアドバイスの中身はそっちのけで「八つ当たり」に必死になる感じ。
・それでも「テストだから同級生全員が練習するんだからやらないとね」と伝え、練習を続行。あまりのできなさに、リコーダーを使わず楽譜の音楽をYoutubeで聞かせてリズムを「手でたたいて」とる、ということをしてみせて、本人もまきこみ、ひたすら曲になじむようにした(ここで音楽のメロディーを暗記させ、リズムというもがあるのだと知らせるのが目的)
・親がリコーダーの手の部分を担当して、子には口で吹かせるだけ(息を吹き込む練習、吹き込む息に強弱をつけないと低い音が高くなり音が割れるので)の二人羽織をした。これは子の方も少し気分もかわり、楽しんだ。
・ここですでに30分以上が経過
・こんなのしてもむりー、できないー、と時々泣いて転がり脱線する子に対して親は「はい、明日テストだからやらないとね」と壊れたレコードのように繰り返して、さらに練習をすすめる
・手の動きで、わからないような所は一つ一つ、教えてゆっくりでもできるように、じわじわと曲をすすめていく(この時点で何度も繰り返しているのでメロディーを暗記しはじめた。すでに楽譜を離れても音がとれそうになってくる)
・1時間ぐらいすると疲れて大パニックしたり大泣きしたりして「やっぱり無理だ!」とキレたりするので、「たかが1時間で吹けるようになると思ってるなら甘いよ。楽器は毎日毎日練習して、やっと1曲ひけるようになるのが当たり前だから。しつこいほど練習して仕上げるのが、楽器。ピアノもバイオリンもリコーダーも同じ。はい、練習しておいで」
と泣き部屋(大パニックして泣き叫ぶ時に、思いっきり安全に泣けるように物をあまりおかない状態で用意してある泣くための部屋)に行かせて、放置する。
・泣き止んだら、少し一人で練習してみたりしはじめるので、そのままさらに泣き部屋に放置。
・たまに泣き部屋から出てきて、親に聞かせてみせたら「上手く吹けない!」とまた失敗して泣き叫ぶけれど、さらに泣き部屋で練習しておいで~と送り出して、放置。
午前中ずっとと、午後に数時間、泣いたり吹いたりを続けて、ということをした結果、曲を自然と丸暗記してしまい、自動的に楽譜を見ながら、「音やリズムを覚えていない・あやふやなまま演奏する」という無謀な状態を脱したので「吹きやすく」なり、その分だけ少し上達して「まあまあ音になってる」ところが増えました。
そうすると、子供側からは文句の垂れ流しが止まり、または泣き叫ばずに練習をしている時間がどんどん延長していきました。そのままやるだけやらせておくと・・・
最終的には、立派とは言えませんが、「まあ曲になってるよね?」と親子ともに思える程度には仕上がりました。
「絶対無理!自分には無理だ!(心の中:練習しても自分にはやれる能力がないもん)」
と本気で思い込んでいた子どもが、その思い込み=自分自身の内面の壁、がちょっと崩れるので、不思議と子どもの気持ちの変化というか、「あれ、こういう風にしてできるようになるんだ」という感じ取るものがあったような雰囲気を見せました。
絶対自分にはできない、無理だ、と言う心の奥底には「認めたくないけど自分は能力的に低い」という自己評価の部分と、それを認めることへの恐れと、その恐れから逃れる方法が「今まで見つからなかった」経験から来る失望などが入り混じった状態で、結果、子どもの心は正直へしゃげた状態です。
「できない」と変な自信を持っている感じでしょうか。ですので、ちょっとした継続した「嫌なことをとことんやる」ということ、イコール、巨大なストレスでしかない、と認識して逃げようとします。その自分の経験不足な方法しか知らないのもあります。
とことんやる、という経験を365日の1日だけでもして、少しだけでも結果的に向上すると、さすがに後ろ向きな子でも「自分のダメな能力で失敗した、という風にはあまり感じない、どちらかというと、とことんやったら少しできるようになった、っていう感じがする。」という、少しですが「良い」結果を、じわじわと、感じてちょっと嬉しそうな顔をしたりします。
努力、と定型の人が呼ぶこの「継続してできないことを少しでもできるように必死にやってみる」行いは、発達障害の子にとって鬼門ではありますが、1年のうちに数回はくぐっておかないと、「努力というもののプロセス自体を知らずに終わってしまう」ことになります。
リコーダーの子は、
「こんなに長い時間、ずっと笛を吹いていたことは今までになかった」
「一日ずっとリコーダーを構えて持ってたから、今までと違う感覚(指がリコーダーに慣れた)」
「曲を覚えてしまった」
「むちゃくちゃ難しいって感じはなくなった。結構、吹ける」
など、「今までとちょっと違う手ごたえ」を感じて、1日中練習したことについての文句は後では出ませんでした。もちろん、自分なりに結果よしと感じ納得したからだと思います。
そもそも、リコーダーのテストで曲を覚えてもいない、という出発点から何か間違ってるのですが、発達障害の子はそういう部分に鈍感です。覚える必要があることを知らなかった、面倒でなかなか吹く、という実践をやらなかったので当然の結果として吹けなかった、という当たり前の部分の経験の欠落が補われて解決しただけなのです。
が、この「当たり前」のプロセスを、本人は「新鮮だ」と感じているのがありありとしていましたので、親は「リコーダーを吹くという実践を何時間もして、曲を覚えて、はじめて結果がでる、という努力のプロセスが経験不足で実感できていないから、すぐに結果を求めて、でもプロセス皆無で結果だけ求めるから失敗して、自分はダメだ!無理なんだ!のこだわり思考に堂々巡りで陥るのね」と、しみじみしていました。
テストですが、そうそう同級生なみに上手く吹けるはずはなかったです。が、今までと違うのは「練習不足なまま学校へ行った」わ�
�ではないので、指になじんだリコーダーで、音が割れながらも1曲を通しで吹けたので、先生も同級生も驚いて大喝采だったそうです。いつもならつかえて演奏が止まりますが、下手でも通しで吹けた=練習をかなりしてきた、と周囲にはわかったのだと思います。
これから、おそらく1ヶ月に数回は、似たような「努力のプロセスを学ぶ」負荷を親は試みる予定です。本人が今回の七転八倒の経験をした結果、まんざらでもなかったからです。主にテスト前の学習でやってみて、結果が少しでも良ければ本人が「これが結果を出すためのやり方なんだ」と実感できやすいだろう、と効果的な課題を選んでいく予定です。
長々と書きました。わかりにくい説明になってしまい、すみません。私達親族の子達が陥りやすい「はしょり思想」、結果をすぐに求める割には、そのための努力をした形跡がまるでない、なのに結果も良い結果を当然として求めるのはなぜか、というその根本の原因やカラクリが少しでも実例の中で伝わればいいな、と思いながら書きました。
ネタは少し変わりますが、他の親族も暗唱のテストだったり、折り紙が折れない!という悩みだったりで同じ「とことんやる」試みをしておりました。その子にとってよさそうなタイミングでトライしてみる一つの方法として、ご紹介してみました。
言動で新しい自分が始まる

グッバイマイサマー宣言してたけど
inプサーーーーーーン!!
イw
でも
ちなみに
最近のすんちゃんから溢れ出るオーラが
取材させて欲しい![]()
![]()
![]() ←
←



![部下がアスペルガーと思ったとき上司が読む本 信じられない言動をする部下の心がわかる あなたは本当に病気なの?[本/雑誌] / 宮尾益知/著 滝口のぞみ/著](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_1114/neobk-2089518.jpg?_ex=256x256)