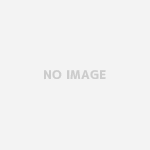近代は何故実装問題を引き起こすか
いまさら聞けないLoRaWAN入門
2017年09月19日
IoTデバイスを開発する上で重要なLPWA(低消費電力広域通信)ネットワークのうち、自前で基地局設置ができることから注目を集めているのが「LoRaWAN」です。本稿では、このLoRaWANについて、利用者視点で解説します。
IoT(モノのインターネット)デバイスが無線通信を行う際に、「低消費電力で長距離のデータ通信を可能とする技術」として注目を浴びているのが「LPWA(Low-Power Wide-Area Network)」です。その中でも“自前で基地局設置ができる”LPWAとして注目を浴びているが「LoRaWAN」です。
本稿では、LoRaWANについて、「どのくらいの通信が可能なのか」「低消費電力とは具体的にどのくらいか」「利用するためには何が必要なのか」「実際の実装の雰囲気は」といった利用者視点から解説していきます。
まずは「LPWA」の定義から
LoRaWANの解説の前に、まずは「LPWA」について確認しておきましょう。
LPWAの明確な定義はありません。しかし、「長距離のデータ通信」そして「低消費電流」という2つの特徴を満たしている通信ネットワークがLPWAと呼ばれています。
通信距離は1kmを超えることが1つの目安です。消費電流については、同じ長距離データ通信として利用されているセルラー通信のモジュールと比較して消費電流が低いことが挙げられます。
例えばLoRaWANのトランシーバー(モデム)の1つである「SX1276」は、データ送信時の消費電流は最大で約30mAです。これはセルラー通信モデムの消費電流と比較しても約16分の1以下ですので、低消費電流と言えます(図1)。
図1 消費電流の違い
LPWAで利用されている技術
LPWAで利用されている無線技術のほとんどが枯れた技術の上に成り立っています。例えば、LoRaWANにおける無線化技術はLoRa変調です。このLoRa変調の開発は2012年ごろに米国のセムテック(Semtech)が行いましたが、基礎となるスペクトラム拡散自体は1980年代に実用化されており、Wi-Fiなどでも使われている技術です。
そのため、IoT向けにLPWAが開発されたわけではなく、旧来から存在してたLPWAの要素技術が提供する「長距離」「低消費電流」そして「狭帯域」という特徴がIoTにマッチしたというのも、LPWAがいま注目されている要因の1つになっています(図2)。
図2 LPWAの位置付け
「ライセンス」「アンラインセス」とは
LPWAを紹介する際「ライセンス系」「アンライセンス系」と分類されることも多くあります。ここで「ライセンス」と言っているのは、利用する無線周波数や運用形態において必要となる「無線局免許」のことを指しています。
電波は有限の資源ですが、簡単に利用できてしまうことから、日本国内において電波を利用した無線通信を行う場合は、原則として「無線局免許」が必要です。根拠法は電波法で、管轄は総務省となります。
「無線局」というと送信機や基地局といった設備だと思いがちですが、設備の運用者といった部分も含めた総体が無線局と定義されています。
LoRaWANは、「無線局免許」が原則不要である「アンライセンス系」LPWAです。
「LoRa」と「LoRaWAN」の違い
解説記事などでLoRaとLoRaWANというそれぞれの単語が混ざっていたりするため、整理のため解説します。
- LoRaは変調方式(データ⇔電波への変換方式)
- LoRaWANはMACレイヤー(L2)によるデータ送受信までを含めた仕様
以上のような違いがあります。そのため変換方式におけるLoRaのことを「変調LoRa(または、LoRa変調)」と称し、LoRaWANと明確に区別することも多くなってきました(図3)。文脈によってはLoRaをLoRaWANとして見る必要もありますので、注意が必要です。
図3 LoRaとLoRaWANの違い
「LoRaWAN」の特徴
レイヤー2を含む「LoRaWAN」はセムテックによって開発されていますが、セムテック自身もメンバーとなっているLoRa Allianceによって仕様などが公開されているグローバルかつオープンな通信方式です。
仕様上はレイヤー構造にはなっていますが、LoRaWANはLoRa変調を使う前提となっており、物理層を別のものに変更して使うことは想定されていません。このLoRa変調ですが、日本国内では2016年11月にアジア向け拡張である「AS923」によって920MHz帯を利用するようになり、それに準拠したモジュールが開発、販売され始めています。
利用周波数ですが国によって異なります。共通しているのは、その国で空いているISMバンド(Industry:産業、Science:科学、Medical:医療で利用可能な周波数帯)を用いるということのみです。そのため、ある国で利用できるモジュールが別の国では利用できないという事態が容易に発生し得ることに留意が必要です。
ペイロードサイズ(プロトコルオーバーヘッドを除いた、開発者が利用できるデータサイズ)が極めて小さいことから、レイヤー2よりも上のプロトコルは規定されておらず、開発者の実装となります。そのためJSON(JavaScript Object Notation)のようなリッチな構造化フォーマットではなく、バイナリによる通信が主体となります(図4)。
図4 LoRaWANのペイロードサイズ
通信距離ですが、障害物や天候などの条件が極めて良い状況で11kmを達成したという実証実験データもあります。しかし、利用する基地局(ゲートウェイ)端末の仕様やアンテナのサイズにもよりますが、業務に利用する場合は屋外で3km程度、屋内や障害物が存在する場合は1km程度での利用が現実的となるでしょう。
またLoRaWANに限らず電波を用いた無線通信全般にいえることですが、金属製の筐体の中または金属の近隣においては電波が乱れたり遮断されることで通信距離が短くなる、または通信ができないということもありえますので、注意が必要です。
しかしながら、2.4GHz帯や5GHz帯を用いた通信に比較すると障害物越しの通信に強いので、適用シーンや設置環境を鑑みて試験してみることが一番大切です。
LoRaWANの利用と商用サービス
LoRaWANを始めるに当たって、一般的にはLoRaWANのデバイスとアプリケーションを準備する他には、ゲートウェイ、ネットワークサーバも利用者自身で準備、構築する必要があります。
国内にお�
�るLoRaWANの商用サービスの提供事業者としては、2017年2月にサービスを開始したソラコムの「SORACOM Air for LoRaWAN」があります。ソラコムのサービスではネットワークサーバがフルマネージドで提供されます(図6)。
図6 「SORACOM Air for LoRaWAN」が提供するLoRaWANシステムの範囲
その他、福岡市で展開されている「Fukuoka City LoRaWAN」においてはネットワークサーバがフルマネージドで提供される他、基地局であるゲートウェイも設置済みのものを利用できます。LoRaWANと同じく有力なLPWAの方式であるSigfoxと同様、デバイスとアプリケーションを用意すれば利用可能なサービスになる見込みです。
全てを自前で準備するのは規模によっては費用対効果が見込めないため、フルマネージドなネットワークサーバと、自前もしくは事業者が設置したゲートウェイを組み合わせて利用する形態が現実的といえるでしょう。
LoRaWANデバイス
LoRaWANを利用するためのハードウェアも充実してきています。これらのハードウェアを利用する場合、デバイス固有のID(DevEUI)をLoRaWANネットワークサーバに登録することで通信が可能となります。ゲートウェイからネットワークサーバなど全てを自営する場合は問題になりませんが、LoRaWAN事業者のサービスを利用する際にはDevEUIの登録が必要となる場合があるため、他方で購入したLoRaWANデバイスが事業者のネットワークサーバで利用できるか確認する必要があります。
基地局(ゲートウェイ)の設置
LoRaWANにおける基地局(LoRaWANではゲートウェイと称します)ですが、日本の場合基本的には利用者自身が設置を行う必要があります。特定小電力無線を利用する、無線局免許が不要な通信となります。そのため原則自由に基地局の運営ができることが最大のメリットです。この「運営」の意味ですが、設置場所はもちろん、設置後の移動やメンテナンスやサービス終了のための停波ということも含まれています。
商用サービスの項目でも紹介しましたが、セルラー通信やSigfox同様に、基地局を設置して提供する事業者も現れています。先に紹介したFukuoka City LoRaWANにおいてはNTTネオメイトと福岡市が、また静岡県藤枝市で行っているLPWA実証実験ではソフトバンクと藤枝市が基地局の設置と運営を行っており、利用者は設置済みの基地局を利用することで、デバイスとアプリケーションの開発に専念できるようになっています。
ここまでは利用者、もしくは単一の事業者それぞれが基地局を設置するモデルを紹介してきましたが、利用者が設置した基地局を共有することで電波という有限の資源を効率よく利用しようという取り組みもあります。商用サービスでも紹介したSORACOM Air for LoRaWANの基地局の「共有モデル」というサービスです。
ソラコムが所有するゲートウェイを利用者が設置し、そのゲートウェイを他の利用者を含めて共有するという仕組みです(図8)。
図8 一般的なLoRaWANゲートウェイの利用とSORACOM Air for LoRaWANにおける共有ゲートウェイの違い
LoRaWAN開発の実際
LoRaWANを利用した実際のIoTデバイスの開発について、SORACOM Air for LoRaWAN の共有ゲートウェイを利用した例を挙げながら解説します。全体像は図9の通りです。デバイス側で必要なものはマイコンとLoRaトランシーバー(モデム相当)です。本例ではマイコンに「Arduino UNO R3」を、LoRaトランシーバーには「Arduino UNO」で利用可能なLoRa開発シールド「AL-050」を利用します。
図9 LoRaWANの開発の実際
マイコン側では下記のようなプログラム(スケッチ)で、LoRaWAN通信が実現できます(図10)。今回利用したAL-050については、ソラコムからArduino用ライブラリが無償公開されているので、それを利用しています。
図10 マイコン側の実装
データの可視化については「SORACOM Harvest」というデータ蓄積・可視化サービスを利用しています。この設定も、SORACOMのWebコンソールから SORACOM Harvestを利用するスイッチをONにするだけでグラフや送信されたJSONテキストを確認できます。
ペイロードサイズが小さいことは既に紹介済みですね。先のプログラム(スケッチ)では、分かりやすさとクラウドでの再利用性を考慮してJSONとして送信していますが、実際の開発においてはバイナリフォーマットが主体となるでしょう。その場合、クラウド側での展開や利用が難しくなります。
本稿で紹介したSORACOMでは「バイナリパーサー機能」によって、バイナリ列をJSONに変換する機能があり、これを利用することでペイロード設計の幅を広げることができるようになっています。こういったサービスが受けられるのも、フルマネージドサービスの利用の利点となるでしょう。
実装 「ただ友」のワを広げよう
今日は私が、初めて鳥の一時預かり組織を作ろう、
と宣言した記事をご紹介します!
見ると日付は2016年1月8日。
気づけば、1年半以上の月日が流れていました。
改めて時間が流れるはやさを感じるとともに、志を抱いてから、現在に至るまでの道のりを冷静に振り返ることが出来ました。
この記事を書いてから、立ち上げスタッフ2名が日本へ帰国し、新たに2名のスタッフが加わって、プログラマーも2度の交代劇がありました。
決して楽ではない道のりで、くじけそうになったこともあり、恐らくこれからも、困難な課題は山積みとなるでしょう。
でもなんとか、多くの方のご支援をいただきながら、公式ウェブサイト公開の一歩手前まで来れました。
道なかば、ならぬ道3/1程度というのが実際です^^;
公式ウェブサイトのテストを、メンバーの方々にもお手伝いいただきながら行っている現在、過去を一度、振り返ることは決して悪くないと思います。
とりきちが昔の記事で書いた内容を見てまいります。
1.サイト=器を作るだけでなく、
地域のコミュニティづくりから積極的に関わる。
顔をすでに知っているまさに「顔見知り」に
預けられる安心感をもってもらえるよう、
様々なイベントを通じて出会いの場を作ります。
⇒これまで複数の説明会、メンバー顔合わせ会を日本各地で実施して、一部の地域では自発的なメンバー同士の集まり、コミュニティが形成されてきました。日本全国にこれが波及するよう、まだまだ力を入れていかなくてはなりません。
公開されるウェブサイトではいわゆるSNS機能を備えていて、メンバー同士の交流が、セキュリティが確保されながら活発に行えます。検索機能を使うと、自分の住む郵便番号から、または都道府県名、市町村名などからメンバーを探すことができます。さらに鳥の名前、種類、メンバーのハンドルネームでも探せて、同じ鳥種のメンバーさまに都道府県をまたいでシッティング依頼ができるようになります。
掲示板機能では、「◎月◎日からうちの鳥を預かっていただける◎県在住の方!」といった掲示板を自ら設けることができるほか、「◎県のメンバー集合!」といったグループ掲示板も作れます。すべてサイト上のメッセンジャーでやりとりが可能で、メッセージがあったことは、メール通知機能ですぐに気付くことができます。
2.利用前の預ける鳥さんの健康診断を義務化し、
事前に契約書を結び、責任の所在を明確にする。
⇒これは、医療関係者の先生方にもご意見を慎重に仰ぎながら、「お預け6ヶ月以内に一般状態、糞便検査、そのう検査を実施し、獣医師により異常なしと判断されている鳥のみ、預けることが可能」としました。メンバーは自らがシッティングする場合、より厳しい健康基準をおのおので設定することもできます。
日本に馴染みが薄い契約書を、
日本の風土に合ったかたちで導入し、
大切な約束事を両者が理解した上で、
利用できるようにします。
⇒契約書も、、利用いただける形とし、現在にいたるまで、お試し預かり、本番のシッティングにもメンバー間で利用されています。やはり、安心感が違うと好評です。とくに友人同士など親しい間柄こそ、こうした書類を用意することで、万が一のときに、友人関係が傷つかないと考えています。
3.預け主、預かり主の両者に評価システムを導入する。
通販システムなどに見られるユーザー評価で、
事前にトラブルを防ぎ、良いシッターさん、
利用者さんを知れるようにします。
⇒こちらは公式ウェブサイトにはまだすぐには実装されない機能です。予算上の都合もあります。しかし、サイトの基本的な機能をまず満たすようにし、次のステップとして可能とする予定で、プログラマーの方にも要望を出しています。レビュー機能実装により、メンバーの中でも、特にたくさんのシッティングをされているシッターさんが誰かも一目瞭然となり、情報の透明性が確保できると思います。
現在はシッター終了報告を、シッター・預け主さまの両者より頂いており、それを、で公開させていただくことで、これから利用を考える方にとって、良い判断材料となるようにしています。
4.運営に常駐スタッフをドイツまたは日本に置き、
必要に応じて利用者同士の仲介に入る。
⇒現在、常駐の事務局スタッフを2名置いて、問い合わせやシッティングの個別依頼、仲介など全てに対応できるようにできています。ウェブサイトが公開されることで、現在、手作業で行っている仲介業務などの事務局の負担も大幅に軽減されていくものと予想されます。
5.制度利用は無料とし、万が一の薬代など実費のみ、
預ける側が原則負担する。
利用料を取るべきとのお声もありましたが、
ドイツで当たり前に行われている相互扶助の理念を
あえて掲げたいと思います。
⇒現在も無料によるサービスの提供をしています。実費分は預け主様の負担で、当初の内容と変わっていません。預け主さまからは、毎回のシッティングの後、善意の寄付もBIRDSITTERSに頂いており、活動資金にあてさせていただいています。ただし、活動資金は決して潤沢ではないため、近い将来、新たな資金集めの活動を計画しています。
6.制度運営に必要な経費は、このシッター制度に
賛同いただく個人の方や団体の方からの
寄付金によりまかない、準備期間の間、
クラウドファンディングにより募る。
⇒この後、実際にクラウドファンディングにより資金集めを実施し、多数のご支援者のもと、初年度から次年度までの活動資金を確保することができました。
7.クラウドファンディングにより寄付いただいた方は、
試運用期間(2016年内)のメンバーとして、
シッター制度を預け主、預かり主として体験いただき、
正式なオープン�
��用開始のための
フィードバックをいただく。
⇒こちらは現在も活発に「お試し預かり」という名のもとで、各地で実施されており、たくさんのフィードバックを頂く形で制度の見直しを行ってきています。詳しくは、、の、複数のシッター終了報告をご覧ください。
お試し預かりを経験された方々は皆、やはり預かってみなくては、または預けてみなくては分からないことがたくさんあると、言われます。お預けが複数回となっても、毎度、愛鳥さんの状況や体調は同じではなく、どれだけ密にシッターと預け主が連携し、臨機応変に対応できるかが大切だと、次第に判ってまいりました。
シッティング前の事前面談も、心配事項を減らし、愛鳥情報を細かに伝える上で非常に重要なステップであることも、終了報告を目に通すことで確信することができました。
8.広く業界団体の方々にもお声をかけ、賛同いただき、
動物を愛する者同士が、個人、団体の枠を超えて
助け合える社会をめざす。
⇒こちらは、現時点では主に案内パンフを置いていただく、顔合わせ会をご提供いただいたフロアで実施させていただくなどにとどまっていますが、今後は、同じく鳥の保護に力を入れておられる団体様との連携も視野に、全国規模の愛鳥家ネットワークづくりを目指して、災害時などのときに、愛鳥さんが露頭に迷うことがないよう、愛鳥家同士が助け合える社会づくりを目指したいと思います。
9.試運用までの期間までは、とりきちが発起人となり、
その運営会社「とりきち横丁」が母体となって、
全面バックアップする。
⇒現在も、とりきち横丁が母体=後援となり、BIRDSITTERSの運営を助けています。具体的にはチャリティグッズの販売や案内パンフの横丁サイト経由の配布、かわら版などの紙媒体での告知などです。日本でのイベント開催時には、BIRDSITTERSにも関心がおありの方に情報提供ができるようにしています。直近ではで、BIRDSITTERSご紹介ブースを置く予定です。
10.2017年内に正式運用へ無事移行できた時点で、
独立した非営利組織となるよう目指す。
⇒まだまだ実現には遠いのですが、NPO法人となることを目標にしています。営利組織である、とりきち横丁から巣立ち、志の高い方に引き継ぎ、そしてBIRDSITTERSが一人の大人として生きていけるまで、きちんと面倒を見たいと思っています。
***
公式ウェブサイトのテストが終わり、無事リリースされるのは、一番早くて10月10日頃となりそうです。この先は、今はプログラマーの方、テストに協力くださっているメンバーさま、スタッフを信じて、振り返ることをせず、ただ前に進んで行こうと思います。
とりきちこと、BIRDSITTERS発起人シシイ家原でした。
BIRDSITTERSの活動記事を
関心を持って読んでくださった方
ありがとうございます。
ブログをぽちっと応援お願いします♪
<小鳥の無料預かり組織バードシッターズ>
新規メンバー登録はこちらからどうぞ:
<イベント関連のお知らせまとめです>
☆10/15(日)とりきち横丁お勉強セミナー&即売会☆
先行即売会にご参加いただけます!
テーマ「ドイツと日本:飼い鳥と自然療法」
お申し込み受付中→
☆とりきち横丁 イベントボランティア募集のおしらせ☆
追加募集中!
もれなくオリジナル横丁Tシャツプレゼント予定!
会場整理、受付、即売会のお手伝いをお願いできる方!
2017年10月15日(日)に東京で開催される
とりきち横丁お勉強セミナー&即売会で
1日ボランティアスタッフとしてご参加くださる方を
募集しております(*´▽`*)
詳細とお申し込み受付中→
☆10/22(日)BIRDSITTERS関西地区顔合わせ会☆
お席が埋まってまいりました!
メンバー登録を検討している方も歓迎です。
お申し込み受付中→
とりきち横丁の を始めました!
ぜひ、いいね!をクリックください♡


![SWD-CL10 OCXO 城下工業 クロックジェネレーター【SWD-CL10 OCXO追加実装モデル】 SoundWarrior(サウンドウォーリア) [SWDCL10OCXサウンドW]【返品種別A】【送料無料】](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0459/4522425050430.jpg?_ex=256x256)
![プロダクションレディマイクロサービス 運用に強い本番対応システムの実装と標準化 [ Susan J Fowler ]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8154/9784873118154.jpg?_ex=256x256)
![実装 ディープラーニング [ 株式会社フォワードネットワーク ]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9993/9784274219993.jpg?_ex=256x256)
![エッセンシャルWPF:Windows Presentation Foundati UI、ドキュメント、メディアの統合に向けた実装と手 (Programmer’s selection) [ クリス・アンダーソン ]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7981/79811420.jpg?_ex=256x256)